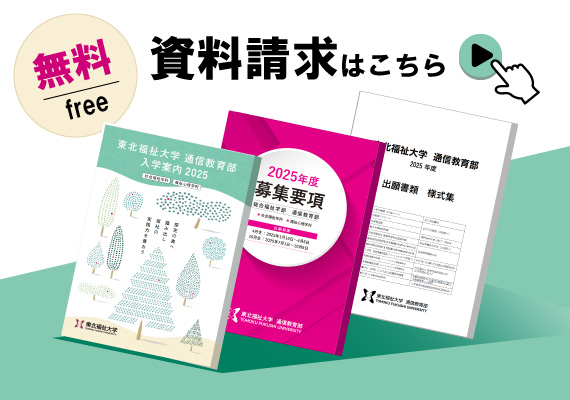本ページの記載内容は2021年度の情報となります。最新の情報は2022年度の『入学案内』・『募集要項』にてご確認ください。
精神保健福祉士
精神保健福祉士とは ―精神保健福祉士法 第2条より―
精神保健福祉士は、精神保健福祉士法の規定に基づいて1997年に誕生した、精神障害者の社会復帰などを援助するソーシャルワーカーであり、名称独占の国家資格です。病気と障害を併せ持つ精神障害により生活に困難をきたした対象者に対し、多様な側面から支援を図る援助相談の専門職として、さまざまなフィールドで活躍しています。2020年9月末の登録者数は90,844名です。
ソーシャルワーカーは、生活に困難をきたしている方に対して、対象者自身とその人を取り巻く環境の両方の側面から問題の緩和・解決を図るための支援を、多職種・多機関と連携しながら行います。
精神保健福祉士が支援する対象者の主な疾患
厚生労働省 平成29年患者調査より
- 気分[感情]障害(躁うつ病を含む)
- 神経性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(不安障害など)
- 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
- 認知症(アルツハイマー病)
- その他の精神及び行動の障害
- てんかん
- 認知症(血管性など)
- 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(アルコール使用〈飲酒〉など)
精神保健福祉士の活躍の場
| 医療機関 | 精神科病院、精神科診療所(医療相談室などで主治医や看護師、臨床心理士などとの連携・調整) |
| 司法施設 | 保護観察所(社会復帰調整官・保護観察官) |
| 行政機関 | 精神保健福祉センター、保健所など(暮らしのサポート) |
| 地域の施設 | 障害福祉サービス事業所など(日常生活訓練・就労支援など) |
| 教育機関 | スクールソーシャルワーカー(学校や家庭、児童相談所、行政機関などとの連携・調整) |
| 企業など | 従業員のメンタルヘルス支援部署(相談や予防などのサポート) |
国家試験受験資格取得のために ―精神保健福祉士法 第7条より―
大学で精神保健福祉士の国家試験受験資格を得るためには、指定科目を単位修得(履修)して、卒業することが要件となります。在籍中にその両方を満たすことで、受験資格を得ることができます。
国家試験は、最短で在籍中の卒業年度に、卒業見込状態で受験することができますが、当該年度(3月末)に指定科目の単位修得および卒業要件を満たすことが、合格が認められる条件です。
また、入学前に指定施設で1年以上の相談援助の実務経験がある方は、実習免除の申請が可能です(詳細は、『募集要項』参照)。
カリキュラム改正について
精神保健福祉士国家試験受験資格に関する法改正のため、精神保健福祉士養成課程の新しいカリキュラム(教育内容)が1年次入学者は令和3(2021)年度から、2年次編入学者は令和4(2022)年度から、3年次編入学者は令和5(2023)年度から順次導入となります。
1年次入学者適用の新カリキュラムの内容は、今後、HPや入学後に配付される『学習の手引き』にてご案内予定です。
本学が精神保健福祉士を目指す学生に求める資質
①精神障害者の権利を擁護する代弁者として、②精神障害者と地域との間を取り持つ調整者として、③精神障害者の生活環境に働きかける伴走者として、相手を受容し、思いやり、困っている状況を改善しようと願う心=「福祉マインド」を持つことが大切です。
そのために、在籍中は、「相手の考える幸福とは何か」、「どのような精神保健福祉士になりたいのか」を考え続け、自分が感じたことを「言葉」と「文字」に置き換えながら、相手に通じるために努力し、工夫することを求めます。
精神保健福祉士 演習・実習指導・実習科目 演習・実習指導の履修方法=SR(レポート+スクーリング)※仙台会場のみ
精神保健福祉士国家試験受験資格取得のためには、演習・実習指導・実習科目の履修が必要です。
演 習:精神保健福祉士の専門的価値を基盤にした「かかわり」を具体的に学びます。
実習指導:理論や概念を実践に適用する意義を、一連の作業(具体的事例)を通じて学びます。
実 習:実践場面での「かかわり」を通して、知識・技術・価値を実践的に理解します。
※上記科目には、期日までにレポート提出や単位修得を要件とする「受講条件」が設定されており、達成した方のみ、次の演習等に進むことができます。演習・実習指導・実習科目の受講条件は毎年見直しを図っているため、入学時の条件とは異なる場合があります。
精神保健福祉援助実習(受講定員:40名程度) 実習科目名は、2・3年次編入学者適用のものになります。
実習は、在籍中の異なる年度に実習A・Bを受講します。2つの実習を同一年度に受講することはできません。
- 「精神保健福祉援助実習A」(福祉施設:3年次)10/1~2/15の中で15日間以上かつ120時間以上
- 「精神保健福祉援助実習B」(医療施設:4年次)7/1~12/25の中で12日間以上かつ90時間以上
入学後、実習受講を希望する全ての方は、入学出願期間中にインターネット配信による「入学前・実習受講者向けガイダンス」の受講が必要です。ガイダンスの内容にご納得いただけない方は、本学通信教育部で実習を受講することはできません。
実習前年度に、「実習選考試験」を実施します(実習免除者を除く)。そのため、希望者全員が実習を受講できるわけではありません。
その他、詳細は『募集要項』参照。
精神保健福祉士国家試験受験資格取得のための指定科目
- 3年次編入学者は、必要最低限となる62単位の指定科目の単位修得で、卒業と受験資格取得可能。
- 1・2年次編入学者は、指定科目の単位修得と併せて、卒業要件(『募集要項』p.12~13参照)の達成も必要。
【1年次入学者対象】精神保健福祉士国家試験受験資格に関する指定科目(予定)
| 厚生労働大臣の指定する精神障害者の 保健及び福祉に関する科目 |
本学の科目名 | 配当年次 | 科目単位 | S単位 | 履修方法 | オンデマンド | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※医学概論 | 医学概論 | 2年以上 | 2 | 1 | RorSR | (注) | |||
| ※心理学と心理的支援 | 福祉心理学 | 1年以上 | 2 | 1 | RorSR | ||||
| ※社会学と社会システム | 社会学と社会システム | 1年以上 | 2 | 1 | RorSR | ||||
| ※社会福祉の原理と政策 | 社会福祉原論A | 2年以上 | 2 | 1 | RorSR | ||||
| 社会福祉原論B | 2年以上 | 2 | 1 | RorSR | |||||
| ※地域福祉と包括的支援体制 | 地域福祉と包括的支援体制A | 2年以上 | 2 | 1 | RorSR | ||||
| 地域福祉と包括的支援体制B | 2年以上 | 2 | 1 | RorSR | |||||
| ※社会保障 | 社会保障論Ⅰ | 3年以上 | 2 | 1 | RorSR | ||||
| 社会保障論Ⅱ | 3年以上 | 2 | 1 | RorSR | |||||
| ※障害者福祉 | 障害者福祉 | 1年以上 | 2 | 1 | RorSR | ||||
| ※権利擁護を支える法制度 | 権利擁護を支える法制度 | 2年以上 | 2 | 1 | RorSR | ||||
| ※刑事司法と福祉 | 刑事司法と福祉 | 2年以上 | 2 | 1 | RorSR | ||||
| ※社会福祉調査の基礎 | 社会福祉調査の基礎 | 2年以上 | 2 | 1 | RorSR | ||||
| 精神医学と精神医療 | 精神医学と精神医療Ⅰ | 3年以上 | 2 | 1 | RorSR | ||||
| 精神医学と精神医療Ⅱ | 3年以上 | 2 | R | ||||||
| 現代の精神保健の課題と支援 | 現代の精神保健の課題と支援Ⅰ | 2年以上 | 2 | 1 | RorSR | ||||
| 現代の精神保健の課題と支援Ⅱ | 2年以上 | 2 | R | ||||||
| ※ソーシャルワークの基盤と専門職 | ソーシャルワークの基盤と専門職 | 2年以上 | 2 | 1 | RorSR | ||||
| 精神保健福祉の原理 | 精神保健福祉の原理Ⅰ | 2年以上 | 2 | 1 | RorSR | ||||
| 精神保健福祉の原理Ⅱ | 2年以上 | 2 | 1 | RorSR | |||||
| ※ソーシャルワークの理論と方法 | ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ | 2年以上 | 2 | 1 | RorSR | ||||
| ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ | 2年以上 | 2 | 1 | RorSR | |||||
| ソーシャルワークの理論と方法(専門) | ソーシャルワークの理論と方法(精神専門)Ⅰ | 3年以上 | 2 | 1 | RorSR | ||||
| ソーシャルワークの理論と方法(精神専門)Ⅱ | 3年以上 | 2 | 1 | RorSR | |||||
| 精神障害リハビリテーション論 | 精神障害リハビリテーション論 | 2年以上 | 2 | 1 | RorSR | ||||
| 精神保健福祉制度論 | 精神保健福祉制度論 | 2年以上 | 2 | 1 | RorSR | ||||
| ※ソーシャルワーク演習 | ソーシャルワーク演習 | 2年以上 | 2 | 1 | SR | 仙台開講 | - | ||
| ソーシャルワーク演習(専門) | 精神保健福祉演習Ⅰ | 3年以上 | 2 | 1 | SR | - | |||
| 精神保健福祉演習Ⅱ | 4年 | 2 | 1 | SR | - | ||||
| ソーシャルワーク実習指導 | 実習免除者は履修不要 | 精神保健福祉実習指導Ⅰ | 3年以上 | 2 | 1 | SR | - | ||
| 精神保健福祉実習指導Ⅱ | 4年 | 2 | 1 | SR | - | ||||
| ソーシャルワーク実習 | 精神保健福祉実習Ⅰ | 3年以上 | 3 | 3 | 実習科目 | - | |||
| 精神保健福祉実習Ⅱ | 4年 | 2 | 2 | 実習科目 | - | ||||
※印:社会福祉士受験資格取得のための指定科目と共通の科目。
(注) オンデマンド・スクーリングの開講予定について
2021年2月現在で、上記科目のオンデマンド・スクーリングの開講は未定となっております。
【2・3年次編入学者対象】精神保健福祉士国家試験受験資格に関する指定科目
| 厚生労働大臣の指定する精神障害者の 保健及び福祉に関する科目 |
本学の科目名 | 配当年次 | 科目単位 | S単位 | 履修方法 | オンデマンド | 大卒者認定可能性(注4) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※人体の構造と機能及び疾病 | のうち1科目 | 医学一般 | 3科目中1科目以上選択で受験資格取得可 | 2年以上 | 2 | 1 | RorSR | ○ | 有 | |
| ※心理学理論と心理的支援 | 福祉心理学 | 1年以上 | 2 | 1 | RorSR | ○ | 有 | |||
| ※社会理論と社会システム | 福祉社会学 | 1年以上 | 4 | 2 | RorSR | - | 有 | |||
| ※現代社会と福祉 | 社会福祉原論(職業指導を含む) | 2年以上 | 4 | 2 | RorSR | ○ | 無 | |||
| ※地域福祉の理論と方法 | 地域福祉論 | 2年以上 | 4 | 2 | RorSR | ○ | 有 | |||
| ※社会保障 | 社会保障論 | 3年以上 | 4 | 2 | RorSR | ○ | 有 | |||
| ※低所得者に対する支援と生活保護制度 | 公的扶助論 | 3年以上 | 2 | 1 | RorSR | ○ | 有 | |||
| ※福祉行財政と福祉計画 | 福祉行財政と福祉計画 | 3年以上 | 2 | 1 | RorSR | ○ | 無(注1) | |||
| ※保健医療サービス | 保健医療サービス論 | 3年以上 | 2 | 1 | RorSR | ○ | 無(注1) | |||
| ※権利擁護と成年後見制度 | 福祉法学 | 2年以上 | 2 | 1 | RorSR | ○ | 無(注1) | |||
| ※障害者に対する支援と障害者自立支援制度 | 障害者福祉論 | 1年以上 | 4 | 2 | RorSR | ○ | 有 | |||
| 精神疾患とその治療 | 精神医学 | 3年以上 | 4 | 2 | RorSR | - | 有 | |||
| 精神保健の課題と支援 | 精神保健学 | 2年以上 | 4 | 1 | RorSR | ○ | 有 | |||
| 精神保健福祉相談援助の基盤(基礎) | 精神保健福祉援助技術総論Ⅰ | 2年以上 | 2 | 1 | RorSR | - | 有 | |||
| 精神保健福祉相談援助の基盤(専門) | 精神保健福祉援助技術総論Ⅱ | 2年以上 | 2 | 1 | RorSR | - | 有 | |||
| 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 | 精神保健福祉の理論 | 2年以上 | 2 | 1 | RorSR | ○ | (注2) | |||
| 精神科リハビリテーション学 | 3年以上 | 4 | 2 | RorSR | ○ | 有 | ||||
| 精神保健福祉援助技術各論 | 2年以上 | 2 | 1 | RorSR | - | 有 | ||||
| 精神保健福祉に関する制度とサービス | 精神保健福祉のサービス | 2年以上 | 2 | 1 | RorSR | ○ | (注2) | |||
| 精神保健福祉の制度 | 3年以上 | 2 | 1 | RorSR | ○ | (注3) | ||||
| 精神障害者の生活支援システム | 精神障害者の生活支援システム | 2年以上 | 1 | 1 | RorSR | ○ | 無 | |||
| 精神保健福祉援助演習(基礎) | 精神保健福祉援助演習A | 2年以上 | 1 | 1 | SR | 仙台開講 | - | 無 | ||
| 精神保健福祉援助演習(専門) | 精神保健福祉援助演習B | 3年以上 | 2 | 1 | SR | - | 無 | |||
| 精神保健福祉援助演習C | 4年 | 2 | 1 | SR | - | 無 | ||||
| 精神保健福祉援助実習指導 | 実習免除者は履修不要 | 精神保健福祉援助実習指導A | 3年以上 | 1 | 1 | SR | - | 実務経験者免除有 | ||
| 精神保健福祉援助実習指導B | 4年 | 1 | 1 | SR | - | |||||
| 精神保健福祉援助実習 | 精神保健福祉援助実習A | 3年以上 | 2 | 2 | 実習科目 | - | ||||
| 精神保健福祉援助実習B | 4年 | 2 | 2 | 実習科目 | - | |||||
※印:社会福祉士受験資格取得のための指定科目と共通の科目。
(注1)2009年度以降に大学に(編)入学して、単位修得した場合、個別に認定される可能性があります。
(注2)本学通信教育部の「精神保健福祉論Ⅰ」および「精神保健福祉論Ⅱ」を2012年度以降に単位修得している場合のみ、「精神保健福祉の理論」および「精神保健福祉のサービス」を個別に認定します。
(注3)本学の「精神保健福祉論Ⅲ」を2009年度以降に単位修得している場合のみ、「精神保健福祉の制度」を個別に認定します。
(注4)大卒者認定可能性:福祉系の四年制大学を卒業した方で、在学中に上記指定科目の単位修得をしている場合は、既修得単位の個別認定ができる可能性があります。くわしくは『募集要項』p.82をご覧ください。
【ご注意】2・3年次編入学者の方へ
2・3年次編入学の上記カリキュラムに対応した国家試験は、2023年度までとなります。
新しいカリキュラムに対応した国家試験が実施される2024年度より、上記カリキュラムは一定期間を設けて閉講し、それ以降は新しいカリキュラムに対応した科目の内容も含めて受講していただくため、学習の負担が増えることが予想されます。そのため、入学後は可能な限り最短年数での国家試験受験資格取得を目指して計画的に学習することをお勧めします。