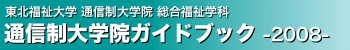V 修士論文
4 修士論文作成
論文は,一昼夜で仕上がるものではなく,膨大な時間がかかります。論文作成の進捗が一定の時期に一定の段階に達していなければ,論文を完成することが難しくなりますので,各段階ごとにレジュメを作成します。以前提出した場合も今年度修了を希望する方は,再度提出してください。また,レジュメ集を作成し教員,他院生(提出した方のみ)に送付します。この試みは,通信制ではなかなか得られない他者からのアドバイス,または他者の研究を知ることでの気づきを狙ったものです。
下記に各段階でのレジュメの内容を記載しています。ただし,あくまでも一例とし,指導前のレジュメ作成や事前に指導が受けられなかったなどの場合に参考としてください。
途切れることなく,研究を進めていくためにどうぞ有効に活用してください。
修士論文作成許可
修士論文を作成するためには,前年度までに学位請求論文研究計画書を提出して指導教員が決定し,下記のように1年次に規定の単位数を修得しておく必要があります。つまり,論文作成の準備として,授業科目の単位の修得もしなければなりません。
万が一,条件を満たせず不許可になった場合は,次年度に条件を整えることになります。
| 入学年度 | 修士論文作成条件 |
|---|---|
| 平成17〜20年度 | 両専攻とも12単位以上 |
| 平成14〜16年度 | 社会福祉学専攻16単位以上,福祉心理学専攻12単位以上 |
構想レジュメ
下記の点を中心にまとめてみましょう。学位請求論文研究計画書の内容を深め,より確かなものとしてください。学位請求論文研究計画書では求められていない論文の枠組み「2.論文構成(案)」を新たに作成してください。
- 論題(仮題でも可):何について研究するのか
- 論文構成(案):どのように論を展開していくのか(章立て)
- 研究の目的:どうしてそれを研究したいのか
- 方法:どのような方法・手順で進め,どこまで明らかにするのか
- 主要参考文献
論文の構想は,建物でいえば骨組みの部分になるかと思います。骨組みが強堅でないと建物は崩れてしまいます。それと同様に構想は論文の骨格です。しっかりと取り組みましょう。
第1回中間レジュメ
論文作成の中間点です。中弛みをしそうなこの時期にご自身の研究を見直してみましょう。修正をするならこの時点です。また,仮説を確固たるものとしましょう。
- 論題(仮題でも可)
- 研究目的・方法:より具体的に書くこと
- 研究内容:章・節構成と仮説を必ず記載すること
- 主要参考文献
第2回中間レジュメ
この時期は,これまで研究してきた内容を文献や調査または実験結果などをもとに少しずつまとめ始めなければなりません。
また,第2回中間レジュメにより,修士論文の提出について検討します。様式15「修士論文提出願」を必ず添付してください(「提出・執筆要領」7. 参照)。進捗状況やどの程度指導を受けているかなどが重要になります。これまでのまとめと考えて,レジュメを作成してください。
- 論題(仮題でも可)
- 目次(章・節構成)
- 研究目的・方法
- 研究内容
- 主要参考文献
レジュメとは別に修士論文の本文がどの程度執筆されているか指導教員から求められる時期です。後に手直しが必要になるかもしれませんが,早い時期にできるところから少しずつ本文を書きためておきましょう。そのためにも論文の構想をしっかり立てておくとよいのです。
レジュメ提出・執筆要領
各レジュメ提出は,下記の1.〜6.をよく読んで間違いのないように提出してください。
- 提出方法は,郵送またはEメール(5枚以内)となります(FAX不可)。
- 本文は,A4判用紙3〜5枚(横書き)でまとめてください。規定枚数以上の場合,超過枚数分省略しますので,予めご了承ください。
- 文字ポイント10.5(論題12ポイント),1ページの印字は1行40字×30行,余白は上下左右とも30mmとしてください。
- レジュメの冒頭に論題,次に学籍番号,氏名,指導教員名を書いてください。各レジュメの内容1.〜4.または5.を本文の見出しとしてください。ただし,既述した見出しについてはあくまでも参考とし,指導教員の指示に従ってください。
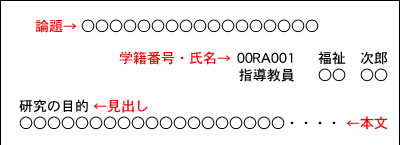
- 両面印刷をせず,ページ数は入れないでください。
- 散乱した場合に備え,右下に学籍番号を記入してください。
- Eメールで第2回中間レジュメを提出する場合,様式15「修士論文提出願」のWordによるフォーマットをお送りしますので,「レポート提出」へお申し込みください。様式15は添付枚数(5枚以内)に含みません。
- 注1)論文を書きためていき,レジュメ作成に論文の一部を抜粋するなどしてレジュメを完成させるか,反対に作成したレジュメを論文に流用して,論文を書き進めていくかなどされるとよいでしょう。無駄な労力と時間を省く1つの方法です。参考にしてください。
- 注2)レジュメ提出は,教員の指導を受けるためではありません。各自の研究を発表する場と考えてください。
そのため,教員の指導は,レジュメの提出前が望ましいのですが,レジュメ作成に時間が取れない,指導を受ける機会がつくれないなどの場合は,レジュメ提出時に通信指導または面接指導を必ず受けるようにしてください(くわしくは「3 修士論文の指導」参照)。