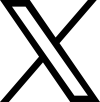2025/07/18 社会福祉学科
社会福祉学を学ぶ人のためのストーリー:福祉を学んで夢を見つける
「個々の特性を生かす支援」や「福祉の多様な分野への広がり」、「人と人とのつながりを作るための知識や技術」、「社会の持続可能性への貢献」など、社会福祉に関する科目では幅広い知識と技術を学びます。それは福祉分野に限られないキャリア形成にも広がっていきます。このお話は大学の社会福祉学科で学ぶイメージを持っていただくための創作ストーリーです。
「福祉の学びが広げた新しい夢 ~旅行で人と人をつなぐ私の挑戦~」
高校時代、「人の役に立ちたい」という思いを抱いて社会福祉学科に進学した彩花。当初は、福祉とは「介護の技術を学び、福祉施設で働くこと」だと漠然と思っていた。
しかし大学の授業が始まると、想像以上に幅広い学びがあることを知る。1年生で受講した「コミュニケーション技法」の授業では、傾聴や共感、自己開示の方法、信頼関係を築くための対話技術などを学び、「福祉とは人と人とのつながりをつくること」だと少しずつ感じ始めた。
2年生:実習で経験した「共同菜園プロジェクト」
2年生の実習では、地域の高齢者と子どもたちが一緒に活動する「共同菜園プロジェクト」に参加。最初は、お互いにどう声をかけてよいかわからず、遠慮気味だった高齢者と子どもたち。彩花は実習で学んだコミュニケーション技法を活かし、高齢者には子どもたちの育てた野菜に関心を持ってもらう話題を振り、子どもたちには高齢者の知恵を尋ねるよう促した。
やがて畑の中には自然な笑顔が増え、世代を超えた会話が生まれるようになった。子どもたちは高齢者から野菜の育て方を学び、高齢者は子どもたちとふれあうことで生き生きとした表情を取り戻していった。彩花はその様子を見て、「人と人とのつながりを作る支援」が、実際に孤立を防ぎ、誰かの生活の中に喜びを生むのだと強く実感した。

3年生:「地域福祉と包括的支援体制」での学び
3年生になると「地域福祉と包括的支援体制」という授業を履修。そこでは、福祉が単なる介護技術だけではなく、住民同士のつながり、支援のネットワークづくり、孤立を未然に防ぐ仕組みが重要であることを学んだ。
授業の中では、ある地域の高齢者サロンの事例を学習。高齢者が毎週集まり、体操や食事、趣味活動を行うことで、孤立せず安心して暮らせる環境ができていた。その中には、地域のボランティアや商店街の協力もあり、多様な立場の人が役割を持ちながらつながっていた。
彩花は「介護をしなくても、人と人をつなげることが支援になり、地域を支えることになる」と実感し、自分の中で福祉のイメージがさらに広がっていった。

ゼミ活動:観光まちづくりプロジェクト
さらに大学のゼミ活動では、地域の観光まちづくりをテーマにしたプロジェクトに参加。少子高齢化の進む地域で、観光を通じた地域活性を考える取り組みだった。
調査を進める中で、彩花は次のような現実に気づいた。
" 超高齢社会の中で、健康で経済的にもゆとりのある「アクティブシニア」が増えている
" 高齢者も旅行やレジャーを楽しみたいが、加齢による身体の変化や健康リスクに配慮が必要
" 車椅子利用者に適した温泉宿、バリアフリールーム、介助者同伴でも安心できる旅行プランの不足
" 介護タクシーや福祉用具レンタルなど、福祉制度やサービスに関する知識が旅行企画にも活用できる
ゼミの中で彩花は、「車椅子でも楽しめる温泉旅行」「介助者と一緒に参加するリハビリ応援ツアー」などの企画アイデアを発表。福祉を学んだからこそ、高齢者本人や家族の不安や要望を具体的に理解し、それに応える旅行プランを提案できる自信が芽生えていった。
就職活動:旅行代理店への挑戦
こうして彩花は、福祉で学んだ「個々の特性を理解し、つながりを作る力」を活かして、旅行業界で高齢者向けの商品開発を行う仕事を目指すようになった。就職活動では、バリアフリー旅行を積極的に扱う旅行会社に応募し、面接でこう語った。
「福祉を学んで、人と人とのつながりが人生の満足度に大きく影響することを学びました。旅行は人を元気にし、思い出を作り、家族との絆を深める機会になります。高齢者や家族の立場を理解できる私だからこそ、誰もが安心して楽しめる旅行を企画したいです。」
________________________________________
福祉の学びは介護や国家資格取得にとどまらず、「人と人とのつながりを作る知識と技術」「多様なニーズに応える視点」「社会の持続可能性を支える力」を身につける学問である。彩花のように、学んだことを活かせる進路は福祉業界に限らず、民間企業やさまざまな社会分野にも広がっている。
- 地域福祉と包括的支援体制A:高齢化や人口減少、福祉ニーズの多様化・複雑化、担い手不足といった現代社会の課題を踏まえ、「誰もが支え合う共生社会の実現」を目指しています。
- 地域福祉と包括的支援体制B:血縁、地縁、社縁といったつながりが弱まっている現状を背景に、「人と人、人と社会がつながり支え合える地域をつくるための方法」を学習します。また、地域共生社会における包括的支援体制のあり方や、それを構築するコミュニティソーシャルワークの方法論について具体的な理解を深めることを目的としており、これはソーシャルキャピタルの概念と深く関連しています。
以下のゼミでは、地域社会が抱える様々な課題に焦点を当て、その解決策やより良い地域社会のあり方について探求します。特に以下のゼミテーマは、ソーシャルキャピタルに関連する視点を含んでいると考えられます。
- 芳賀 恭司 担当: 多様な背景を持つ人々の共生を可能にする福祉コミュニティーのあり方について考え、「共生社会」の実現や「住み良い地域とは何か」を考察します。地域住民との交流を通じて、共生社会に必要な要素を探求します。
- 菅原 里江 担当: 社会で起きている出来事を多様な視点で理解し、「社会」と「人」とのつながりを理解することの重要性を学びます。身の回りの社会生活にある「なぜ」を追求し、考える力を養うことが目的とされています。
- 田中 尚 担当: 共生社会や持続可能な社会の実現目標の中で、社会福祉問題は重要課題であり、人と人との「つながりの構築」はソーシャルワークの根幹に関わる課題であるとしています。
- 大石 剛史 担当 (リエゾンゼミⅢのみ): 地域における共生社会(ケアリングコミュニティ)の実現に関心を持ち、新しい人々の生活実態や社会構造の中で、新たなつながりをいかにして構築できるかというテーマを深く探求します。フィールドワークや実地調査を通じて自らの考えを構築することを目指しています。
- 小野 芳秀 担当: 地域が抱える福祉的課題の改善を目指し、地域共生社会の実現に向けた地域コミュニティの向上、支援システム(仕組み)の構築が不可欠であるとし、これらについて検討します。
- 千葉 伸彦 担当: 地域における子どもを取り巻く環境や子育て支援に関する問題を発見し、問題を解決するための具体的な計画や社会資源の開発を行い、子どもや家族が安心して住み続けられる地域について考察を深めます。地域の様々な社会資源と連携することも目標に挙げられています。
- 清水 冬樹 担当: 大学近郊における子どもの居場所づくりを実践することを通して、地域における子ども支援の価値を理解し、コミュニティワークとコミュニティソーシャルワークについて学びます。
これらの科目では、人々の信頼関係、規範、ネットワーク、そしてそれらがもたらす地域社会の機能や活力といった側面について、理論的、実践的に学ぶ機会が得られると考えられます。特に、地域福祉、地域共生社会、地域課題の解決、人とのつながり、コミュニティーといったキーワードに注目してシラバスを確認すると、ソーシャルキャピタルに関連する学びを見つけられるでしょう。