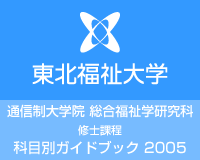
東北福祉大学 通信制大学院 総合福祉学研究科
| 担当教員● | 三浦 文夫 |
|---|
テーマ
福祉国家の揺らぎと国家福祉の動向
戦後の多くの国々での国家目標とされた福祉国家は、1970年代末ぐらいから、その「揺らぎ」を見せ始めてきている。イギリスのサッチャーイズム、アメリカのレーガノミックス(その亜流ともいうべき日本の中曽根内閣の第二臨調路線)の登場は、福祉国家に対するアンチテーゼと目されるが、その流れのなかで多くの国々で福祉国家の「揺らぎ」ともいうべき動きがみられます。その「揺らぎ」の具体的な現れとして、ジェームス・ミッジリのいう国家福祉の変容を捉えることができます。この演習では福祉国家と国家福祉との関係を考察しながら、福祉国家の「揺らぎ」あるいは「修正」のなかで国家福祉の変容がどのように行われているのかを研究するとともに、そのなかでの日本の社会福祉の転換の道筋と課題について検討することにしたいと思います。その問題意識のもとで、演習では次のようなテーマを取り上げ検討する予定です。
■演習で検討する課題
- 福祉国家と国家福祉
- 福祉国家の展開とその「限界」について(イギリスを中心に)
- 福祉国家と国家福祉の変容(福祉の多元化と民営化の動向)
- 比較福祉の視点からみた日本の社会保障(とくに社会福祉)の特徴
スクーリングの事前課題
スクーリングでは上記課題の3「福祉国家と国家福祉の変容」を中心に討議を行いたいと計画しているので、とくに参考文献3と4についてあらかじめ読んでおいてください。(なお、スクリーリングには参考文献の3と4を持参してください)
スクーリングの事後課題
課題1 |
比較福祉の観点から見た日本の福祉政策(社会保障、社会福祉等)の再編とその特色(あるいは特異性)について考察せよ。 |
|---|
アドバイス
課題1 |
サッチャーイズム、レーガノミックスなどの台頭のなかで、イギリス、アメリカその他の国々では戦後型の福祉政策の見直しが行われてきているが、わが国でも第2臨調による行財政改革と同調するかのように、社会福祉は戦後型社会福祉からの転換をめざし、さまざまな提言や改革が行われてきています。このなかで1990年の「老人福祉法等8法改正」が現れ、その流れはさらに社会福祉基礎構造改革を経て2000年の「社会福祉事業等8法改正」につながってきています。それと平行するかのようにゴールドプランの策定、介護保険の創設、2004年の公的年金制度等の改正も行われ、21世紀型社会保障、社会福祉の再構築が重要な潮流となっています。このなかで社会保障あるいは社会福祉における政府の役割はとくに注目されることになっています。換言するといわゆる大きな政府から小さな政府への転換のなかでの社会保障、社会福祉の再編が行われてきているとみることもできます。このような状況原価のなかでの最近のわが国における社会保障、社会福祉の変容をどのようにみるかという問題意識のもとで課題を設定しました。 |
|---|
参考文献
(赤字=大学から送付される必読図書)
- エスピアン・アンデルセン 岡沢・宮本訳『福祉資本主義の三つの世界』ミネルヴァ書房、2001年
- 岡沢憲芙・宮本太郎編『比較福祉国家』法律文化社、1997年
- 大山博、炭谷茂,武川正吾、平岡公一編『福祉国家への視座』ミネルヴァ書房、2000 年
- ジェームス・ミッジリ 京極、萩原等監訳『国際福祉論』中央法規出版、1999年
- 三浦文夫『増補改定 社会福祉政策研究』全国社会福祉協議会、1995年
- 厚生労働省『厚生労働白書 平成18年版』