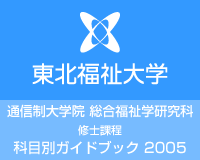
東北福祉大学 通信制大学院 総合福祉学研究科
| 担当教員● | 木村 進 |
|---|
テーマ
虐待への福祉心理学的アプロ−チ
近年「児童虐待」が大きな社会問題となってきており、遅ればせながら日本でも「児童虐待等防止法」が制定されている。また、例えば「保育所保育指針」にも「虐待」の項目が設けられ、その発見と通告を通して虐待の防止に努力することが義務づけられている。また、虐待についての一般的な関心の高まりから、「虐待と周囲から思われるのではないか」という不安が子育て中の親にあることも、いろいろな事例から明らかになっている。
このように考えてくると、虐待の問題は、単に虐待を起こしている家族やその被害者である子どもに限定されるものではなく、まさに社会的問題であるといえるのである。あるいは、単に虐待を行う親が特殊な人間であるという認識は間違っており、どんな親でもその可能性を秘めているということかもしれない。
そういう意味から、この問題を福祉心理学の課題としてとりあげ、その防止について追求することは、虐待という行為を越えて、子育ての問題、子どもの教育の問題、さらには親のあり方の問題を考える上でのきわめて適切な材料であると思われる。そして、さらには、日本の現代社会において、子どもがどのような位置付けにあり、どのように一個の人間として尊重されているかということにも論が及ぶことになろう。
本演習においては、以上のような背景における広がりを念頭に置きながら、虐待の実態、その発生機序、子どもへの影響等について学ぶことを第一の目標とする。
演習は、次のような内容から構成されている。
- 論文 ORGANIZING A HUMAN SERVICES NETWORK FOR PRIMARY AND SECONDARY PREVENTION OF THE EMOTIONAL AND PHYSICAL NEGLECT AND ABUSE OF CHILDREN を読む
- 新聞記事等を参考にして、虐待を起こす(母)親の現実についてまとめる
- 文献により、虐待の発生機序、子どもへの影響について理解する
- 虐待防止の方策について考察する
このうち、1がスク−リングの主な内容となり、残りは、各自が文献や資料を集めて学習を進めることになる。
■研究の視点
- 虐待研究の歴史とその概念の変遷、定義
- 虐待を起こす親の条件・環境的条件についての理解
- 虐待の子どもへの影響、特にパ−ソナリティへの影響
- 虐待防止への取り組み、特にアメリカにおける取り組み
スクーリングの事前課題
スク−リングまでに、事前に配布する上記1の論文を自分なりに訳し、内容を理解して持参すること。スク−リングにおいては、訳や理解が不十分な点について補うとともに、内容理解をより深めるための資料によるディスカッションを行う。
スクーリングの事後課題
課題1 |
虐待の発生は、親の条件、子どもの条件、環境の条件の3方向からとらえられるのが一般的である。虐待の定義を明らかにした上で、これらの条件について、研究結果を基にしてまとめなさい。ここで研究結果というのは、公刊された論文という意味である。 |
|---|---|
課題2 |
以下の3問のうち1問を選択してレポ−トしなさい。
|
アドバイス
課題1 |
課題は、虐待を理解するための基本的設定であるから、極言すれば虐待に関する参考書を1冊手に入れれば書けるものである。しかし、そういう抽象的一般的な理解では不十分なので、新聞や雑誌の記事、あるいは、市販されている手記など、さらには身近に虐待の事例があればそれらを使って、具体的な内容にする努力を期待している。 また、「研究結果を基にして」とあるのは、虐待の発生要因について、どのような研究が行われ、どのように分析され、そして、どのような結論が得られているかということを論文を通して知ることによって、レポ−トの内容に確実性を保証するとともに、研究というものが、どのように行われるのかということについての理解を促進することを期待している。そのことは、修士論文のための研究を行う際に、必ず役立つはずである。 研究論文を手に入れることが難しい人もいると思われるが、スク−リングの際に大学図書館を利用するとか、あるいは、その際に文献検索の方法および複写依頼の方法を学習して、必要な論文を手に入れる方法を身につけてほしい。 |
|---|---|
課題2-1 |
虐待は、子どもの発達のさまざまな面に悪影響を与えることは言うまでもないが、どのような面にどのような影響があるかということを、ここでは、総合的に考察する。この場合も、結論だけを述べるのではなく、できれば、その結論の基になった研究についても言及してほしい。また、いずれにせよ参考図書を見つけてそれに頼るしかないわけであるが、影響をどのようにまとめるかという点にレポ−トの評価があることを知っておいてほしい。 |
課題2-2 |
虐待防止については、さまざまな角度からの対策が考えれれなければならないが、日本ではまだその緒についただけの段階である。その点、30年以上前からこの問題に取り組み、制度化してきたアメリカにおける実践は、虐待防止対策を考える上で参考になると思われる。アメリカにおける対策を明らかにした上で、それを日本に導入したらどうかということについて論じてほしい。 |
課題2-3 |
この課題は、1とは違って、焦点をかなり絞った課題である。多重人格ということが知られるようになってきているが、性的虐待の結果として生じるということも指摘されている。この課題では、多重人格ということについて説明し、その上で、性的虐待との関連において生じた多重人格の例をいくつか述べる。さらに、多重人格の治療にも言及することが望ましい。 |
参考文献
(赤字=大学から送付される必読図書)
- 西澤 哲 1994 『子どもの虐待──子どもと家族への治療的アプロ−チ』誠信書房
- 田村健二 1984 「日本における児童虐待とその防止」『東洋大学社会学研究所年報』22巻
- 池田由子 1979 「被虐待児の研究」『精神衛生研究』26号
- 池田由子 1984 「ある被虐待児と親の治療例」『現代のエスプリ』206号 至文堂
- 池田由子 1987 『児童虐待:ゆがんだ親子関係』 中央公論社