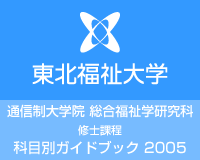
東北福祉大学 通信制大学院 総合福祉学研究科
| 担当教員● | 宇田川一夫 皆川 州正 |
|---|
宇田川 一夫 担当分
テーマ
力動的心理療法の過程
心理療法の種類は、多種多様です。ここではその代表のひとつとして「力動的」立場に立つ心理療法を取り上げます。
力動的心理療法に立つ心理療法としては、フロイト派の「精神分析」、ユング派「分析心理学」が代表であり、その理論を背景にて「箱庭療法」「家族療法」「心理劇」「集団精神療法」「芸術療法」等が発展しています。
そのためまず、これらの力動的心理療法の特徴は、何かを学習する必要があります。
次に、力動的心理療法は、具体的にどのような心理療法を行うのか、事例を通して検討していきます。
心理療法の過程には、「見立て」「面接過程」が重要なテーマとなります。
「見立て」とは、主訴、生育歴、パーソナリティ特徴等から、面接目標を立てます。そして、それに基づき面接を行いますが、「面接過程」とは、面接のなかでクライエントと面接者の関係の中で心理的に何が起こっているのか(それを力動といいます)を理解していくことが大切となります。
ここでは、事例をとりあげ、「見立て」と「面接過程」の学習をしていきます。
なお、レポートは参考文献や本等の「要約」ではなく、自分なりに「要約」したことを参照しつつレポート課題について考察し、論述してください。
■研究の視点
- 力動的心理療法の理解
- 力動的心理療法と他の心理療法の相違
- 事例検討とは
- 「見立て」について
- 「面接過程」について
レポート課題
課題1 |
参考文献に上げた事例をひとつ選び、力動的心理療法の立場から「見立て」と「面接過程」を事例検討しなさい。どの事例を扱ったか、文献名とページを明示しなさい。 |
|---|
参考文献
(赤字=大学から送付される必読図書)
- 丸田俊彦著 1986『サイコセラピー練習帳』岩崎学術出版社
- 水島恵一著 1973『カウンセリング入門』大日本図書
皆川 州正 担当分
テーマ
ブリーフ・セラピー
ミルトン・エリクソン(Milton Erickson)は、それまでとは全く異なった心理療法を試みました。たとえば、次のようなものです。
「エリクソンは、州立病院で、自分をイエス・キリストだと主張する患者に近づき、君には大工の経験があるんだってね、と声をかけた。イエスの父、ヨゼフが大工であり、イエスには当然父を手伝った経験があったわけだから、患者は、はい、と答えるしかなかった。またエリクソンは、君は仲間たちの役に立ちたいと思っているんだってね、とも言った。患者はこれにも、もちろん、と答えた。そう聞いておいて、エリクソンは、病院には本棚が足りなくて作らなくちゃならないんだが、君は手伝ってくれるかい、と尋ねた。患者は同意し、症状行動の代わりに、建設的な活動に参加し始めるようになった」
(オハンロン「ミルトン・エリクソン入門」より)。
エリクソンは、催眠療法家でしたので、催眠療法を応用した小さな介入で、クライエントの問題にアプローチしました。しかし、エリクソンは自らのアプローチを体系づけることはしませんでした。そこで、エリクソンのもとで学んだ人たちが彼のアプローチの体系づけを試みました。それが今日ブリーフ・セラピーと呼ばれるものです。そのブリーフ・セラピーも、MRI(
本特講では、ブリーフ・セラピーをマスターすることをめざします。
まず、エリクソンの柔軟な発想や独創的な取り組み方について学習します。
次に、ブリーフ・セラピーについて学習します。問題志向アプローチ、解決志向アプローチ、その両方のアプローチを含んで独自な展開を試みた可能性療法、日本になじむようにアレンジした小野直広によるブリーフ・セラピーをとりあげます。
■研究の視点
- エリクソンの視点
- ブリーフ・セラピーにおけるセラピストの態度
- ブリーフ・セラピーの進め方
- ブリーフ・セラピーにおける介入
レポート課題
課題2 |
ブリーフ・セラピーにおける介入について、実施するにあたって留意すべきこと、介入パターン、介入がクライエントに及ぼす心理的なメカニズムについて考察した上で、介入の一つを実際に行ってみた実践例を報告しなさい。 |
|---|
アドバイス
課題2 |
留意すべきことには、セラピストの態度、クライエントのタイプ、介入する前にやっておくべきことなどがあります。介入パターンは基本的考え方、フィッシュらによるもの、小野によるもの、黒沢によるものと分けて分類を試みてみるとよいでしょう。小野によるものでは、事例の要点も参考にしてください。介入がクライエントに及ぼす心理的なメカニズムは、テキストにある事例をもとに誰かとロールプレイをしてクライエント役をやってみると実感としてわかります。それをもとに考察してみてください。実践例は小野直広『107錠のこころの即効薬』を参考にして職場や家庭などで実際に行ってみてください。 |
|---|
参考文献
(赤字=大学から送付される必読図書)
- P・ディヤング、I・K・バーグ 2000『解決のための面接技法』金剛出版
- R・フィッシュ、J・H・ウィークランド、L・シーガル 1986『変化の技法』金剛出版
- J・ヘイリー 2001『ミルトン・エリクソン子どもと家族を語る』金剛出版
- 今城周造編 2004『福祉の時代の心理学』ぎょうせい(第11章3(2)・5、第13章3(8)・4(2)参照)
- 黒沢幸子 2002『指導援助に役立つスクールカウンセリング・ワークブック』金子書房
- 宮田敬一 1994『ブリーフセラピー入門』金鋼出版
- B・オハンロン、S・ビードル 1999『可能性療法』誠信書房
- 小野直広 1995『こころの相談』日総研
- 小野直広 1998『107錠のこころの即効薬』日総研(絶版のため1章と4章をコピーで配布します)
- J・K・ザイク 1993『ミルトン・エリクソンの心理療法』二瓶社