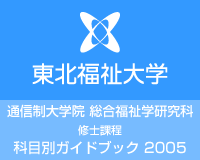
東北福祉大学 通信制大学院 総合福祉学研究科
| 担当教員● | 阿部 裕二 |
|---|
テーマ
社会保障の存在意義と理念・価値
第2次世界大戦後の経済・政治・社会の制度が歴史的に大きな変革の時期を迎えている中で、社会保障も急速に進展する少子高齢社会や危機的財政状況、そしてグローバルな環境問題などを背景として、構造的転換期を迎えている。近年では、介護保険の導入に加え、年金改革、医療(保険)改革、社会福祉基礎構造改革等が行われた。これらは、制度の公平化・効率化・長期安定化(持続可能性)、自助・自己決定の尊重、市場化・民営化、規制緩和、地方分権、IT化などの視点から改革が推し進められている。
しかしながら、このような時にこそ「社会保障」を原点に立ち返って「なぜ我々の社会に社会保障なるシステムが存在しなければならないのか」、「社会保障に内在する理念や価値をどのように理解するのか」などの再検討が求められていると思われる。
したがって、本講座では「構造的転換期にある社会保障」を理解するためにも、社会保障の理念や価値を巡る論争を理解しながら、これからの社会保障のあり方を模索することを目的としている。したがって、本講座においては、個々の制度(医療や年金、生活保護など)を詳細に取り上げることはしない。
■研究の視点
- 社会保障は生成にはどのような特徴があったか。
- 社会保障は過去や現在においてどのように理解されてきたか。
- なぜ私達の社会に社会保障なるものが存在するのか(必然性について)。
- 社会保障における理念や価値をどのように考えるか。
- あるべき(新しい)社会保障に対する自己の見解の構築。
レポート課題
課題1 |
歴史的・相対的概念である社会保障は、過去と現在においてどのように理解されていたか(いるか)を述べた上で、社会保障というシステムがわれわれの社会に存在する必然性について述べなさい。 |
|---|---|
課題2 |
近年、これからの社会保障のあり方を構築する際には、「潜在能力・自由」や「平等理論」などの価値原理の議論がなされているが、それらはどのような意味をもち、社会保障に如何に位置づけられるべきか、それぞれについて述べなさい。 |
アドバイス
課題1 |
そもそも社会保障は、どのような背景(意図)において登場してきたのか、かつ、当時の社会保障は如何なる役割を果たしていたのかなどをまず考察する。そして、今日の社会保障の意味と役割について整理することが肝要である。その際、日本のみならず国際的にも視野を広げると、日本の特殊性が際立つと思われる。 さらに、このような社会保障がわれわれの社会に存在する理由を「市場の失敗」も含めて様々説かれているが、これらの内容を整理・まとめてみることが必要である。 |
|---|---|
課題2 |
社会保障に内在する理念や価値原理はさまざま挙げることができるが、ここでは、「潜在能力と自由」と「平等原理」に焦点を絞り、考察すること。「潜在能力と自由」に関しては、アマルティア・セン(Sen,Amartya)が代表的論者であり、「平等原理」に関しては、ドゥオーキン(Dworkin,Ronald)やレーマー(Roemer,John E .)が著名であるが、まず、彼らがどのような議論を展開しているのかを整理する。そして、そのような理念や価値原理が社会保障に如何に位置づけられるのかについて、自分なりに考察することが肝要である。 |
参考文献
(赤字=大学から送付される必読図書)
- アマルティア・セン(池本・野上・佐藤訳)『不平等の再検討——潜在能力と自由』岩波書店、1999
- 一圓光彌『自ら築く福祉——普遍的な社会保障をもとめて』大蔵省印刷局、1993年
- 大野吉輝『社会保障政策論』勁草書房、1999年
- 塩野谷・鈴村・後藤編『福祉の公共哲学』東京大学出版会、2004年
- 広井良典『定常型社会——新しい「豊かさ」の構想』岩波新書、2001年
- 堀勝洋編『社会保障読本(第3版)』東洋経済新報社、2004年
- 正村公宏『福祉国家から福祉社会へ——福祉の思想と保障の原理』筑摩書房、2000年
- 森健一・阿部裕二編著『構造的転換期の社会保障——その理論と現実』中央法規出版、2002年