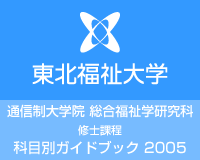
東北福祉大学 通信制大学院 総合福祉学研究科
| 担当教員● | 渡部 純夫 |
|---|
テーマ
ライフサイクルにおける発達の課題と解決へのアプローチ:生涯発達の観点とカウンセリング的結びつき
20世紀は「児童心理学」が発展し、子どもに関心が注がれた時代であった。その結果、多くの研究がなされ、「子どもは小さな大人ではない」(ルソー)ことも科学的に明らかにされるようになった。子どもは発達し続ける存在であり、「児童心理学」はこの意味からも「発達」の一領域を担うようになった。また、生涯発達への関心が高まる中、乳幼児期から青年期までの発達の問題を取り上げるだけでは不充分なことも分かってきた。胎児期から死にいたるまでの生涯にわたる発達を考える必要性が生まれたのである。超音波診断法の技術開発が進み、胎児の研究が急速に進んだ。一方、今までは青年期以降人間の心身の機能は発達しないと考えられていたものが、中年期はもとより老年期でも発達し続ける面がたくさんあることがわかってきた。生涯発達という観点が必要になってきたのである。
生涯発達の考え方は、連続的な自己成長の過程におけるライフサイクルの視点を提供している。どのように生きどのように死んでいくのかという問題を投げかけてくることになる。その問題に取り組むために、発達の課題をどのように取り扱うかが重要になってくる。そこで、連続的なものである生涯を仮にいくつかの時期に分け(ライフステージ)、その時期時期における課題を考えていく方法が浮かび上がることになる。この手法は、エリクソン(Erikson,E.H.)の発達理論にも使われている。
生涯発達の考え方のもと、すべての人が何の問題もなく発達課題をこなしていければいいのだが、現実はそのようにはなっていない。人は、社会的環境に適応しようとする心理的努力のなかで生じるストレスや緊張を時にもてあましてしまうこともある。基本的には、心理・社会的危機を克服しながら、人は発達し続ける存在なのであるが、それがかなわなくなった時、どのように対応したらよいのかという問題が持ちあがってくることになる。
例えば、母親が子育てをしている時、子どもが思い通りにならず叩いてしまったとする。その時不思議な快感を感じ、その後ことあるごとに子どもを叩き怪我までさせるようになったとしよう。このとき、子育ては家庭の問題だから母親に任せ、まわりの人間は関わらなくていいということにはならない。どう関わるかが問われたとき、この発達臨床学の視点が必要になってくるのである。
本特講では、まず生涯発達の観点からみたライフサイクルの発達課題について学習する。特に漸成理論(epigenetic theory)と呼ばれているエリクソンの発達理論について学習しておくことが重要と考えている。
そして、発達理論を理解した上で、発達課題でつまずいた人にどのように関わればいいのかを学んでいくことにする。実践場面で、どのように「発達」と「臨床」を生かせるかが重要なポイントになる。
■研究の視点
- エリクソンの心理・社会的危機理論をはじめとする生涯発達理論の理解
- 発達における家族の意味
- 学校・地域での発達の意味
- 発達上の問題行動
- 発達の障害の理解
- ライフステージから見たつまずきと関わり方
レポート課題
課題1 |
生涯発達という観点からライフサイクルを考え、ライフステージの課題をエリクソンと他の理論家を1人以上選び比較しながら、家族や学校・地域社会が果たす役割と合わせて検討しなさい。 |
|---|---|
課題2 |
発達課題でつまずいた事例を取り上げ、まず事例の概要(家族歴・生育歴・病歴など)を説明し、関わりのポイントを時間を追って説明しなさい。最後に、その事例全般について考察をしなさい。 |
アドバイス
課題1 |
|
|---|---|
課題2 |
自分が関わりを持ったことのある発達課題でつまずいた事例を取り上げ、事例の概要がよく分かるようにまとめる。そのさい守秘義務には十分注意を払うこと。そして、関わりのポイント(クライエントの変化・カウンセラーの考えの流れ・やり取りの中で気づいたことなど)を説明し、考察を加える。 |
参考文献
(赤字=大学から送付される必読図書)
- 氏家達夫 1996『親になるプロセス』金子書房
- 山本真理子 1997『現代の若い母親たち』新曜社
- 齋藤 学 1994『児童虐待』金剛出版
- 下山晴彦編 1998『教育心理学Ⅱ』東京大学出版会
- 石隈利紀 1999『学校心理学』誠信書房
- Deci, E. L.石田梅男訳 1980『自己決定の心理学』誠信書房
- 生島 浩・村松 励編 1998『非行臨床の実践』金剛出版
- 岡本夏木・三宅和夫編 1976『心理学5発達』有斐閣双書
- エリクソン, E. H.仁科弥生訳 1977『幼児期と社会1 』みすず書房
- メイヤ, H. W.1977『児童心理学三つの理論—エリクソン・ピアジェ・シアーズ』黎明書房
- 杉原一昭・海保博之編 1986『事例で学ぶ教育心理学』福村出版
- 杉原一昭編 2001『事例でみる発達と臨床』北大路書房