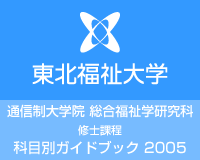
東北福祉大学 通信制大学院 総合福祉学研究科
| 担当教員● | 志田 民吉 |
|---|
テーマ
各種の権利宣言や諸原則、憲法、社会福祉諸法制の人権規定についての研究を主題とします。当該研究の履修目的は、人権制度の全容を理解することにあり、その研究の手法としては、年代別に示された各種宣言や各種法制度間の内容の比較を通じて、人の生存に関わる価値が社会の中においてどのような発見がなされ、どのように具体的に表現されてきたかについて研究します。
レポート課題
課題1 |
「何故に人は生きる権利があるのか」を考え、憲法や各種の権利条約(例えば老人福祉法、国際人権規約、高齢者のための国際連合原則など)に描かれた高齢者の人権の内容についてまとめなさい。事例を挙げながら説明しても構わない。 |
|---|---|
課題2 |
社会福祉領域における「権利擁護制度」について述べなさい。また、それぞの制度を簡単にまとめ、社会福祉サービスの利用者の権利の向上にどの様に貢献するのかについて考え、まとめなさい。 |
アドバイス
課題1 |
この課題は「人はなぜ生きるのか」という素朴な疑問の存在が前提になります。この課題に答えた後に、ではどのように生きることが「人が生きる」ということなのかにつながります。広く宗教学や哲学、臨床心理学の領域にも関心を持つことは必要ですが、さしあたり「法の役割」と併せて、課題に挙げた憲法や条約、各種人権宣言などを参考にしながら、各自自由に考え、まとめてください。この課題のねらいは、人権を理解するための前段階としての必要な事項の理解です。人間とは何かの理解がないままに、人間がどのように生きるのがよいのか、そのためにはどのような権利(利益)享受の保障が必要なのかを考えることです。 |
|---|---|
課題2 |
各種の権利擁護制度の全容を理解しながら、それぞれの制度の目的を明確にし、併せて制度運用の実際における課題にも論及できることを望みます。社会福祉基礎構造改革の内容や社会福祉法の規定に配慮しながらまとめてください。施設などの社会福祉の職場の事例を挙げながら考えてみるとわかりやすいのではないかと思います。 |
参考文献
(赤字=大学から送付される必読図書)
- 志田民吉編著『社会福祉サービスと法』(建帛社)
- 佐藤 進・河野正輝編『新現代社会福祉法入門』(法律文化社)
- 橋本弘子『福祉行政と法』(尚学社)
- 小川政亮『社会保障裁判』(ミネルヴァ書房)
- 池永 満『患者の権利』(九州大学出版会)
- 河野正輝『社会福祉の権利構造』(有斐閣)
- Michael Freeden "Rights" (University of Minnesota Press)。日本語翻訳もあります。
- 志田民吉編共著『法学』(建帛社)
- 志田民吉共著『里親制度の国際比較研究』(ミネルヴァ書房)
- 志田民吉編著『臨床に必要な人権と権利擁護』(弘文堂)
などがありますが、福祉法制度の入門書としては1の文献が相応しいでしょうが、学部で法学を専攻した経歴がない場合には、8及び10で法の役割や人権の理解を併せて行うことをお勧めします。
以上の他に、『月刊福祉』増刊号・施策資料シリーズなどの資料集が市販されていますので、政府刊行物センターなどに問い合わせてください。