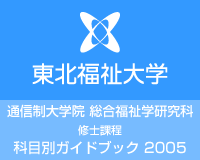
東北福祉大学 通信制大学院 総合福祉学研究科
| 担当教員● | 小笠原浩一 |
|---|
テーマ
ケア・システムの改革
過去10年ほどの間に、福祉的ケアに関する政策動向に大きな構造変化が生じてきている。欧州では、保健、医療、リハビリ、介護といった各専門領域を横に連携させる「統合的ケアIntegrated Care」が今後の標準モデルとなっている。そこでは、高齢者、障害者、難病患者、在宅療養者などに対して、1つの制度の中で、多職種がシームレス(縫い目なく)に連携し、継続的・包括的にクライアントの自立を支えつづける仕組みが考案されつつある。
わが国においても、改正介護保険制度や第5次医療制度改革において、「地域包括ケア」システムあるいは「地域クライアントパス」連携の仕組みへと移行し、やはり、多職種が連携して継続的・包括的に利用者を支える仕組みが進められている。
また、これに伴って、予防的ケアからターミナルケアまでの切れ目のない連続的サービス提供の考え方や認知症の進行段階に即した医療措置と介護サービスとの最適な組み合わせの開発なども進められている。
そこで、この演習では、このような国の内外における新しいケア・システムの動きをテーマとして、(1)政策レベルでの変化が実際にどのように起こっているのか、(2)制度にはどのように反映してきているのか、(3)政策や制度の動きに対応して、ケアサービスならびにその提供システムにおいてどのような新しい考え方が研究レベルから提起されているのか、といった論点について、多角的に学ぶこととする。
■研究の視点
- 「地域包括ケア」「地域連携」といった考え方がなぜ登場したのか
- 従来の「地域福祉」とどこが異なるのか
- 欧州における「統合的ケア」と日本の「地域包括ケア」との異同
- 「地域包括ケア」は利用者にとってどんな利益をもたらすのか
- 予防からターミナルまでという連続的なケア・システムは、利用者にとってどんな利益をもたらすのか
スクーリングの事前課題
第5次医療制度改革で登場した「地域クライアントパス」という考え方、それから介護保険法改正に登場した「地域包括ケア」という考え方は、いったい、いつ頃から、どのような意味で、提案され始めた考え方なのか、ウェブサイト情報などを頼りに、まとめてきてください。
スクーリングの事後課題
地域という枠組みで、保健、医療・看護、リハビリ、ソーシャルワーク、介護ケアを連携して提供するためには、それぞれの専門性と全体のスムーズな連携の両立という観点から、どのようなシステム上の工夫が求められるか、具体的な先行事例を参考にしながら、図を用いるなどして、わかりやすくまとめなさい。
アドバイス
山口県「公立みつぎ総合病院」の長年にわたる地域包括ケアの取り組み、同じく尾道市医師会の地域連携の取り組みなどを、具体的に調べてみてください。たくさんのヒントが得られます。
参考文献
(赤字=大学から送付される必読図書)
- 「社会福祉政策研究」を参照してください。