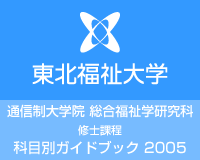
東北福祉大学 通信制大学院 総合福祉学研究科
| 担当教員● | 遠藤 克子 |
|---|
テーマ
「地域生活支援」における社会福祉援助技術活用の課題—日本における社会福祉援助技術の導入と受容をめぐって─
■問題意識
地域生活の継続は本来的には制度やシステムの有無、整備状況の程度にかかわらず、福祉サービスを必要としてきた人びとにとっては当たり前の要求でした。この、10数年、国は社会福祉基礎構造改革を福祉需要の変化に応じて、福祉サービスを提供する場を地域・生活の場と捉え、サービス提供は「措置」から「利用」へと大きく転換し、この方向は制度的には各福祉分野で「地域生活支援」事業と言う形態で提示されてきています。
「地域生活支援」は個人の生活という全体的・継続的・個別的・主体的状況に関わるので、総合的な視点が大切といわれています。
一方、日本においては名称独占ですが国家資格となった「社会福祉士・精神保健福祉士」に限っても社会福祉専門職は専門職としてはまだ制度的にも、専門職としても日が浅く、よく言われる医療・保健・福祉の連携の中では弱小勢力です。また、社会福祉専門職そのものを他の専門職や社会一般の人々がどう認知しているかを考えると、たとえば、社会福祉分野の資格が増えたと言う程度の認識に留まる場合も多く、不十分と言わざるを得ません。また、福祉サービス利用において重視されている「自己決定」という判断・行動がわれわれの生活習慣の中にどう展開しているかという課題もあります。「ケアマネジメント」の導入により、援助者も社会福祉専門職に限らず、専門分化された社会の様々な制度を具現化している職種が関わってきているという現実もあります。
以上を踏まえて、社会福祉専門職が「地域生活支援」の現場でその実践能力を充分に発揮していく事(ソーシャルワークの展開)が、「地域生活支援」を必要としている人々の利益・人権を守る事であり、かつ、社会福祉専門職の社会的認知、専門性の成熟につながることと考えます。いまだ不十分なソーシャルワークが展開される社会システムの整備が大きな課題です。この課題の一端について、受講生がそれぞれレポート課題を通して考察することが、この科目の狙いです。
■研究の視点・前提
- まず、前提として社会福祉援助技術の基本的な概念・方法論を確認・履修すること,特に「エコロジカル・システム・アプローチ」視点の理解。
- 利用者の自己決定を尊重する視点。
- 「福祉臨床」の視点。ここでは個人・小集団・家族について、利用者の主体性・自己決定を尊重する立場で、地域の中で生活している人々の「暮らしと人間関係」に同時に注目し、理解し、ともに、課題解決に向かうと言う視点です。なお、入所施設も周知のように地域の中に含まれます。
- 社会福祉援助技術の基本的知識の確認—基本的面接技術、原則、展開過程など(社会福祉系学科以外の他学科出身者は社会福祉援助術論の基礎は自習してください。学部の授業聴講あるいは社会福祉援助論のテキストを熟読する方法もあります)。
レポート課題の例示
- 連携のあり方(社会福祉専門職と他職種との連携に関するもの)
- 日本人の自己決定について(社会福祉専門職の実践とのかかわりから)
- 社会福祉専門職の新しい役割の導入に関わる課題−例示:日本のケアマネジメント実践に関わる課題など−
- 当事者活動に関する課題(社会福祉専門職との関連で論じる)
レポート課題
上記の1から4の課題の範囲から、関心のあるテーマを2つ選択してください。更に、例示した課題そのままではなくそこから、具体的な各自のテーマを設定しましょう。参考書はレポートを書くための最低のものであり、その他の参考書については申し出があれば学生の個々の課題に応じて,相談にのります。ご自分でも資料・文献を探してみてください。なお、ケアマネジメント関係の文献はたくさんありますので、ご自分でお選びください。
アドバイス
お申し出があれば、課題選択の相談に応じますが、以下をとりあえず参考にしてください。
- まず問題意識および研究の視点・前提の部分をよく理解してください。
- レポート課題作成の前提としては、その課題に関わる社会福祉各分野の現状の「地域生活支援」対策・制度をご自分でよく理解することが大切です。
- 社会福祉専門職の範囲を今回は主として社会福祉士、精神保健福祉士と考えています。しかし、国家資格をもたなくても、ソーシャルワーカーとして仕事をしている人々、あるいは相談業務にもっぱら従事している人々と考えてもかまいません。その際にご自分はどの範囲を論じるのかを明確にしてください。介護支援専門員のアイデンテイという課題も面白いでしょう。
- 文献・注の表示は、日本社会福祉学会投稿規定を参照してください。
参考文献
(赤字=大学から送付される必読図書)
- 平山 尚・平山佳須美・黒木保博・宮岡京子共著 『社会福祉実践の新潮流』 ミネルヴァ書房、1998年
- 山崎美貴子・遠藤興一・北川清一編『社会福祉援助活動のパラダイム─転換期の実践理論』 相川書房、2003年
- F.P.バイステック著 尾崎 新・福田俊子訳『ケースワークの原則(新訳)』 誠信書房、1996年
- メリー・E・リッチモンド 小松源助訳『ソーシャル・ケース・ワークとは何か』 中央法規、1991年
- 大島 巌編著 『新しいコミュニテイ作りと精神障害者施設』 星和書店、1992年
- ヤンネ・ラーション、 アンデシュ・ベリストローム、 アン・マリー・ステンハンマン 河東田博・ハンソン友子・杉田穏子訳『スウェーデンにおける施設解体』 現代書館、2000年
- 『新版③ 社会福祉援助技術論Ⅰ、Ⅱ』 中央法規、2006年
- 一番ヶ瀬康子・大友信勝・日本学校社会事業学校連盟 編著『戦後社会福祉教育の五十年』 ミネルヴァ書房、1998年
- 平山尚・武田丈・呉栽喜・藤井美和・李政元共著『ソーシャルワーカーのための社会福祉調査法』(MINERVA福祉専門職セミナー9) ミネルヴァ書房、2003年
- 日本社会福祉士会編『社会福祉士事例集2 』 中央法規、2001年
- 阿部謹也『学問と「世間」』 岩波新書、2001年
- 中村雄一郎『臨床の知とは何か』 岩波新書、1992年
- 日本社会福祉学会投稿規定