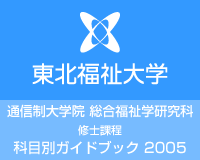
東北福祉大学 通信制大学院 総合福祉学研究科
| 担当教員● | 雪江 美久 |
|---|
テーマ
社会学的生活研究の「理論と方法」について
■ねらい
社会科学の世界では、これまでも私たちの生活に関わる研究手法をさまざまな形で開発し、発展させてきた。特に「社会現象を人間の生活の共同という視点から追求する学問である」社会学にとっては、私たちの生活をどのように“体系的、構造的”にとらえるかはきわめて重要な研究課題であり、それをとらえる「理論と方法」の構築は大きなテーマであった。
社会の急速な発展に伴い、人々の生活の有り様は多様化し、それに伴って噴出する生活問題は一層複雑化の傾向を示すこととなったが、このような状況に対処するために当然のことながら、学問体系の専門化、細分化が急速にすすみ、人々の生活実態を把握する方法もますます精緻化の度合いを深めることとなった。しかし、このような傾向が強まれば強まるほど科学的に把握される「生活」は現実から切り離され、部分化された形でとらえられることとなった。
かかる動きは一面では多くの研究成果をあげ、評価されてきたが、反面であまりにも専門分化されたがゆえに、とらえられた部分が現実から乖離してしまう傾向が強まり、新たに生活現実を、より“トータル”な“ありのままの姿”で、あるいは、より“体系的、構造的”にとらえる「理論と方法」の開発ないし構築の必要性が求められることとなった。とりわけ前述したように「社会現象を人間の生活の共同という視点から追求する学問である」社会学の領域では、この点に関する関心はひときわ強く、さまざまな視点から、かかる「理論と方法」の開発と構築を目指して取り組んできた経緯がある。「生活構造理論」と呼ばれてきた理論はまさにその流れのなかで生まれ、発展してきた「生活研究の理論と方法」であるといってよい。
こんにち、教育や社会福祉に関わる専門領域では、具体的施策を企画立案し、それを効果的に実践していくために人々の生活を的確に把握し、そこに生じている問題を発見し、解決のための方策をさぐることは基本的必要事項となっている。それだけに「生活研究の理論と方法」に関する問題はますます切実かつ重要になっている。
「本研究」では、主として社会学研究においてこれまでに構築されてきた「生活構造理論」に焦点をあて、専門領域における実践場面で求められている実践能力形成のための基礎を学ぶことを目的とする。その際、こんにちの生活研究にとってまず基本的に押さえておきたい問題である、人類社会の発展についての基本的認識の確認の問題と、それに深く関係して問われなくてはならない私たちの生活の“豊かさ”と“便利さ”に関する考え方を検討し(「課題1」)、それに続いて「生活研究の理論と方法」に関する問題(「課題2」)について学ぶことにする。「本研究」の学習内容を項目別に示すと下記の4項目になる。
〔主な学習項目〕
- 人類社会発展の限界とその超克に関する考え方についての考察。
- 文明の高度化と生活の“豊かさ”“便利さ”“安全性”についての考察。
- 生活研究の「理論と方法」についての理解。
- 実践的課題に対応する生活研究の具体的手法についての検討。
(注意)
-
別に開講している「生活構造演習」では、「本研究」が理論的学習に重点を置いているのに対して、具体的事象に直接関わりながら「生活構造理論」の有効性について学ぶ予定である。
◇レポート作成にあたって
- 「本研究」については、以下で説明する「課題1」と「課題2」についての2 つの
レポートの提出を求める。
ただし、「課題1 」は「サブ・レポート」として「課題1 A」と「課題1 B」の2 つの レポートの提出を求める。 - レポートの作成にあたっては、随時、受講生の求めに応じて個別指導を行なうが、基本的な留意事項については下記に記す。
- 各レポートの字数は1課題4000字をメドとするが、それを超えてもよい。ただし、「課題1」については「サブ・レポート」として2つのレポートの提出を求めるので、一つの「サブ・レポート」は2000字、二つの「サブ・レポート」を合わせて4000字をメドとする。
- 各レポートの「評価」は、提出されたレポート内容と面接時および必要によって実施する質疑応答の結果を総合して行なう。場合によっては、追加レポートを求めることがある。
アドバイス
すでに説明したとおり、「課題1」は2つの「サブ・レポート」により作成するが、「課題1 」全体で求める「ねらい」は下記のとおりである。
■ねらい
各種の統計資料が示しているとおり、わが国は昭和30年代中頃から40年代中頃にかけて、すさまじい勢いで経済社会を発展させた。この時期は、いわゆる「高度経済成長期」として世界的にも注目された時期である。この時期を迎えるまで国民生活にはまだ戦後色も色濃く残っており、多くの国民は今では想像もできないほどの貧しさに追われていた。したがって、この貧しさからの解放がなによりもの願いであり、国民生活の向上は、まず日常的な生活財の確保、それも“質よりも、まず量”を充足することが最大のねらいであったといっても決して過言ではない。
しかし、奇跡的ともいわれる高度経済成長期を経るなかで、国民生活は急速に向上し、国民的願いであった“貧しさからの解放”は見事に達成され、世界有数の経済的に“豊かな国”の仲間入りを成し遂げた。国民の平均所得は予想以上に増大し、耐久消費財の普及も目を見張るものとなった。だが、このような急速な社会変化は、国民生活を潤す反面、目を覆いたくなるような問題をさまざまな形で噴出させることとなった。いわば、私たちは自分自身の左手で高度経済成長をすすめ、ある種の豊かさを手にし、その恩恵に浸り、喜びながら、一方で自分の右手で首を締め、その苦しさにもがきながら助けを求めるような状況をつくりだすこととなった。公害問題、自然・環境破壊問題、さては地球温暖化など、数えきれない問題が噴出し、地球規模での問題解決の必要性が叫ばれている。それは科学技術の世界に関連してのみでなく、人間形成や人間の精神生活全般にかかわっても深刻な問題を生みだしている。「豊かさのなかの貧困」といった問題はまさにそれを象徴しているといってよい。
このような状況にあって、科学技術をさらに発展させ、富の分配に関する公平・公正な方法を開発し、平和を実現し、維持していくための科学の発展に取り組んでいくことは緊急課題であるが、同時に、これまでの人間生活のあり方、あるいは社会発展のあり方そのものについても再考を要する課題が突き付けられていることに気づかねばならない。加えて、私たち自身の“真の賢さ”を形成し、その“実践力”を高めていくことがきわめて重要かつ必要となっている。どんなにすばらしい科学を身近に用意しても、それを使う人間が愚かであるならばどうであろうか。
高度なテクノロジー時代(IT革命も含めて)を迎えて、改めて、社会の発展とは何か、豊かさとは何か、あるいは便利さとは何か、といった問題についての認識を再確認していくことが、いま必要課題となっている。この点は私たちの“真の人間的賢さ”を形成していくうえでもきわめて重要であり、これからの生活問題を考えていくにあたって、まさに根本的な問題でもあるといってもよい。この問題は「生活研究の理論と方法」の問題を学ぶにあたって前提的問題である。
課題1A |
持続可能な社会の発展について |
|---|
■ねらい
これまでの経済社会や科学技術の発展は、人類社会に限りない光=豊かさを与えてきた。しかし、一方で自然・環境破壊や、人間生活の有り様に思わぬ影=問題をつくり出してきている。いま、私たちはこのような社会の発展のあり方を振り返り、より望ましい生活のあり方を求め、その実現に向けて努力することが必要となっている。
そこでまず、わが国を含め工業先進国を中心とした社会の発展の仕方についての問題点について学ぼう。そこにはどのような問題があり、さらに今後も人類社会を発展させていくためにはどのような問題があるのかを考えてみよう。この問題は私たちの生活の有り様を考えていく際に基本となる問題であることに気づきたい。この点を主として下記の参考文献を基本的テキストとして学ぶ。
■「レポート課題1A」を作成する要領
字 数: |
約2000字(これを超えてもよい) |
|---|---|
テーマ: |
持続可能な社会の発展について。 |
内 容: |
下記の参考文献のうち、 2 )『生きるための選択 限界を超えて』(D.H メドウス他著、茅 陽一監訳・ダイヤモンド社)を通読し、読書感想と「テーマ」について私見をまとめる。 なお、参考文献の読み方、利用の仕方、レポートのまとめ方などについては、後日改めて指示することがある。 なお、下記の参考文献1 )は、参考文献2 )に先立って出版されたものであり、世界の識者に問題を提起した著名の文献であるので、本レポート作成にあたって一読をすすめたい。 |
■参考文献:
(赤字=大学から送付される必読図書)
- D.H メドウス他 大木佐武郎監訳 『ローマ・クラブ「人類の危機」レポート 成長の限界』 ダイヤモンド社、1972年
- D.H メドウス他 茅 陽一監訳 『生きるための選択 限界を超えて』 ダイヤモンド社、1992年
課題1B |
豊かさとは何か、便利さとは何か |
|---|
■ねらい
溢れんばかりの豊かさと便利さのなかで生活している私たちにとって、現状の生活を“あたりまえのもの”として受けとめている場合が多い。とくに、高度経済成長期以降に生まれた世代は、この豊かさ、便利さについてはいとも当然のものとして受け入れているように思われる。しかし、ちょっと資料を調べて見ればわかるように、私たちがこの豊かさ、便利さを手にしはじめてまだそんなに時間は経っていない。いわゆる高度経済成長期を境に奇跡的な経済社会の発展がもたらしたものである。そのスピードはまさに驚異的なものであった。しかし、そのスピードが驚異的であっただけに国民生活の変化も急激であり、結果として都市問題、公害問題、環境問題、人間性喪失といった諸問題・諸矛盾をさまざまな形で社会生活の場面に噴出させることになった。確かに科学技術の発展に支えられた豊かな経済社会の到来は、国民生活にさんさんと光を照らしてくれたが、反面で暗い影をつくりだし、改めて社会の発展のあり方、とくに経済優先の社会発展のあり方に大きな疑問を抱くこととなった。
よくいわれてきたことではあるが、このような社会の発展のあり方に対して「物から、心へ」とか「経済優先の社会から、人間優先の社会へ」といったキーワードを使って、高度経済成長期に示された社会のあり方、生活のあり方に対する見直しがなされ、それに代わる社会の、そして生活のあり方が求められるようになった。
私たちはここで改めて、戦後の貧しさからの解放を求めて成し遂げた高度経済成長により、何を手にし、何を失い、何を犠牲にしてきたのか、一体、人間にとっての豊かさとは何か、便利さは何をもたらし、何を失うのかといった根源的な問題への問いかけをしていくことが必要になってきているように思われる。これからの生活を展望し、誰もが望む生活を実現しようとするとき、この種の問いかけは一層重要度を増しているといえよう。
■「レポート課題1B」を作成する要領
字 数: |
約2000字(これを超えてもよい) |
|---|---|
テーマ: |
豊かさとは何か、便利さとは何か |
内 容: |
下記の参考文献のうち、3)『豊かさとは何か』『豊かさの条件』(暉峻淑子、岩波新書)を通読し、感想と「テーマ」について私見をまとめる。 なお、参考文献の読み方、利用の仕方、レポートのまとめ方等については、後日、改めて指示することがある。 |
■参考文献:
(赤字=大学から送付される必読図書)
- 暉峻 淑子 『豊かさとは何か』 岩波新書、1990年
- 暉峻 淑子 『豊かさの条件』 岩波新書、2003年
- E.F.シューマッハー 小島・酒井訳『スモール イズ ビューティフル−人間中心の経済学−』講談社、1986年
- 佐伯 啓思『人間は進歩してきたのか——「西欧近代」再考』PHP研究所、2003年
- 佐伯 啓思『「欲望」と資本主義——終りなき拡張の論理』講談社、1993年
- 佐伯 啓思『成長経済の終焉——資本主義の限界と「豊かさ」の再定義』ダイヤモンド社、2003年
- 村上陽一郎『安全学』青土社、1993年
(課題1A・1B に共通)
課題2 |
社会学的生活研究の理論と方法 |
|---|
■ねらい
「課題1 」では、2つの「サブ・レポート」を通じて、主として、現代社会においてなんらかの形で生活研究をすすめていく際に基本的に理解し、再確認しておきたい問題に焦点をしぼり、学ぶことを目的にしていたのに対して、「課題2 」では、実際に生活研究をすすめていく際に必要となる「生活研究の理論と方法」について、主として社会学研究の領域における研究成果をふまえながら、学ぶことにする。
これまでにも社会科学の各分野において「生活」をテーマにさまざまな研究が展開されてきた。既に本研究のテーマのところで解説したように、生活問題が多様化、複雑化してきている現代社会にあって、人々の生活をいかに“トータル”に、“ありのまま”に、また“体系的、構造的”にとらえるか、そしてそのための「理論と方法」をいかに構築していくかは研究者のみならず教育や社会福祉の領域にかかわる専門家にとっても大きな関心事であり、その研究成果が期待されてきた。生活を経済現象の側面からとらえようとする経済学の領域では、早くから貧困の問題や労働者の生活問題などに関連して生活研究を展開してきており、社会学の領域では、まさに「社会現象を人間の生活の共同という視点から追求する学問」にふさわしく多様な問題意識にもとづく「生活研究」が展開されてきた。
特に、戦後期においては民主化の動きと経済社会の発展により、戦前、戦後と続いてきた日本人の生活のあり方や生活文化は大きく、かつ急速に変化し、生活問題に対する関心を高めることとなった。とりわけ高度経済成長期を境に示されてきた社会変化は、地域社会をはじめ、家族、地域集団を拠点として展開される生活のあり方に大きな変化をもたらすことになった。当然のことながら、このような変化がもたらす生活のあり方への影響とそこから派生する問題を的確にとらえるための「理論と方法」を構築することは社会学研究にとって大きな課題となった。以後、社会学研究の領域においては、種々の問題意識のもとでの理論構築が試みられ、こんにちにいたっている。いわゆる「生活構造論」ないし「生活構造理論」の誕生である。「本研究」においては、このような経緯のなかで構築されてきた「社会学的生活研究の理論と方法」を概観し、それぞれの特徴を理解する。そして最終的には、教育や社会福祉の領域で実践的課題に取り組んでいく際に求められる基礎能力の形成を図ることをねらいとする。
■「レポート課題2」を作成する要領
字 数: |
約4000字(これを超えてもよい) |
|---|---|
テーマ: |
社会学的生活研究の方法について |
内 容: |
下記の参考文献のうち、 1 )『生活の構造的把握の理論−新しい生活構造論の構築をめざして』(渡辺益男、川島書店)の「序章 生活の理論の問題とその課題」と「第1章 社会学的生活構造論」を読み、次の3つの課題についてまとめる。その他の章についても読んでおくことが望ましい。
なお、参考文献の読み方、利用の仕方、レポートのまとめ方等については、後日、改めて指示することがある。 |
■参考文献:
(赤字=大学から送付される必読図書)
- 渡辺益男 『生活の構造的把握の理論−新しい生活構造論の構築をめざして』 川島書店、2000年(一部をコピーして配布する)
- 三浦典子・森岡清志・佐々木衛編 『生活構造(リーディングス日本の社会学)』 東京大学出版会、1994年
- 中根芳一編著 『私たちの生活科学』 理工学社、2001年
- 松村祥子 『現代生活論』 放送大学教育振興会、2000年
なお、以上の他に「本研究」に関する参考文献については必要に応じて紹介する。