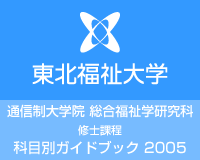
東北福祉大学 通信制大学院 総合福祉学研究科
| 担当教員● | 小笠原浩一 |
|---|
テーマ
社会福祉改革における公私関係の変容と社会福祉基礎構造改革の諸相
戦後わが国の社会福祉政策は、社会福祉事業に対する「公の支配」と措置制度を柱とする「日本的公私関係」を特徴とするものであった。「日本的公私関係」は、1950年の新生活保護法の制定で確立したいわゆる「福祉三法体制」と翌年の社会福祉事業法による基礎構造の整備に具体化されている。「日本的公私関係」は、社会福祉における強い公的責任を特徴としており、比較制度論的にも特異な内容を有するものであった。それは、戦後わが国に特殊な政治社会事情を反映したものであった。
「日本的公私関係」は、社会福祉が一部の国民の貧困問題と密接に結びついていた時代にはそれなりの有効性を維持できた。しかし、国民皆保険・皆年金体制への移行に伴い社会福祉政策の重心が救貧対策からシフトするとともに、高齢化の進展に伴って福祉ニーズが普遍化・多様化するなかで在宅やコミュニティにおけるサービス供給の重要性が増すことになると、その限界や問題性を露呈することとなった。1970年代以降の社会福祉改革の議論は、そのような背景をもって展開し、供給多元化や公私役割分担が政策選択の焦点となった。
1980年代になると、深刻化する財政問題が加わる形で、補助金や委任事務のあり方を見直す動きなどとも一体となって、「日本的公私関係」を制度面で修正するための社会福祉改革が、福祉関係三審議会合同企画分科会における作業やその結果としての「福祉八法改正」などの形で具体的に進むことになる。1990年代には、国際的な社会福祉理念の新たな展開等の要素を付け加えながら、社会福祉基礎構造改革へと展開し、介護保険制度の創設や社会福祉法の制定が実現することになる。2000年代に入ると、地域包括ケアの考え方のもとに、更に新しい展開が見られるようになる。
この科目では、一連の政策展開や制度改革において、「日本的公私関係」のどの部分について、どの範囲で、どのような内容の変化が生じたことになるのか、社会福祉における公私関係の変容と基礎構造改革の諸相という視点から学習し、福祉政策の基本構図を理解することになる。
■研究の視点
- 「日本的公私関係」とは、制度面ではどのような内容を有していたか。
- 「日本的公私関係」の問題点・限界が指摘されるようになったのはなぜか。
- 「日本的公私関係」は民間社会福祉事業の自立を遅らせたと言われるが、なぜか。
- 「福祉八法改正」で、「日本的公私関係」はどの範囲で修正されることとなったか。
- 社会福祉基礎構造改革は「日本的公私関係」の抜本的見直しと言えるか。
レポート課題
課題1 |
社会福祉政策における「日本的公私関係」について、その制度的内容を述べた上で、なぜそのような特殊な「公私関係」ができあがったのか、説明しなさい。 |
|---|---|
課題2 |
1980年代に福祉三審議会合同企画分科会を中心に推進され、最終的には「福祉八法改正」に帰着した社会福祉改革の第1期と、1990年代の社会福祉基礎構造改革を経て社会福祉法に成果を見た社会福祉改革の第2期について、改革の主要なテーマと内容を比較して整理した上で、基礎構造改革によって現れた社会福祉政策における変化についてまとめなさい。 |
アドバイス
課題1 |
社会福祉法人の仕組み、措置制度の仕組み、旧社会福祉事業法第5条の経営準則の仕組みなど、戦後わが国の社会福祉実施体制に関わる仕組みを総体として捉えて、その全体の構造とそれができあがった経緯を考える。また、そうした日本的な公私関係が比較制度論的にどのような特殊性を有していたかにも着目する。 |
|---|---|
課題2 |
第1期で目指されたサービス供給の多元化・分権化ということと、第2期で目指された措置制度廃止ということとの関係について着目し、第2期の改革が内包する2つの側面、すなわち、第1期で残された課題を継承した側面と、1990年代に現れた新たな社会福祉課題に対応する側面についてまとめなさい。また、第2期の改革は社会福祉の基礎構造の改革を目指したものと言われるが、社会福祉法と旧社会福祉事業法を比較して、大きく変化した面と、変わらずに継続している面とに着目して、整理しなさい。 |
参考文献
(赤字=大学から送付される必読図書)
- 北場 勉『戦後「措置制度」の成立と変容』法律文化社、2005年
- 三浦文夫『増補改訂 社会福祉政策研究──福祉政策と福祉改革』全国社会福祉協議会、1995年
- 三浦文夫・橋本正明・小笠原浩一編『社会福祉の新次元──基礎構造改革の理念と針路』中央法規出版、1999年(序章および第1章)
- 小笠原浩一・武川正吾『福祉国家の変貌』東信堂、2002年
- 小笠原浩一・平野方紹『社会福祉政策研究の課題——三浦理論の検証』中央法規出版、2004年