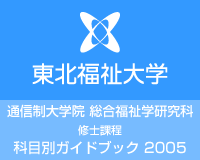
東北福祉大学 通信制大学院 総合福祉学研究科
| 担当教員● | 小松 洋吉 |
|---|
テーマ
少子・高齢社会における福祉サービスの利用者負担
少子・高齢社会が進展してきている。それにともなって、福祉サービスに対するニーズも多様化、高度化してきている。たとえば、少子社会には種々の子育て支援が必要であったり、高齢社会には、地域密着型サービスの充実が必要であったりする。こうしたサービスの諸給付には、相応の財源確保がされなければならない。先進諸国をみてみると、対GNP比で20%を超えている国が普通であるといってよい。わが国の債務残高約800兆円をかかえ、国民のニーズに応えていくことは財政的に容易でない。
サービス充実のための財源として考えられるのは、まず税金、社会保険料、利用者の負担、措入金等である。税でまかなおうとすれば増税をはかるか、他の支出を押さえることになる。かりに増税をすれば可処分所得が減り、消費が減退し、景気が一層冷え込むことが予想される。他の支出を抑え、福祉サービスに用いれば、サービスのバランスを欠くことにつながるかもしれない。社会保険料によって賄うためには、被保険者と事業主の一方または双方の負担が増えることになる。措入金によることは、将来に負担を強いることになり、現実には相当の無理がある。また、積立金の運用によって賄うにも、国民に負担を課することになる。利用者負担による財源確保も同様である。
先進国のサービスの財源構成はさまざまである。いくつかの基本的組合せが考えられる。これらを今後どう考えていったらよいのかについても重要な課題である。
福祉は今「Negativeな福祉」から「Positiveな福祉」の転換的局面にある。介護保険等でみられるようにどのような形であれ利用者負担導入の考えが近年一つの流れであり、今後ますます増大するものと考えられる。この利用者負担の在り方をテーマとする。
■研究の視点
- 少子化・高齢化・人口減少社会の到来について理解を深める。 (これについては参考文献1 )のpp.190〜203を参照)
- 社会保障が行われる経済学的根拠についての理解。 (これについては参考文献2 )のpp.1〜33を参照)
- サービスの財源構成についての理解。 (これについては参考文献2 )のpp.105〜137を参照)
- 利用者負担の機能、メリットについての理解。 (これについては参考文献2 )のpp.70〜84、pp.149〜168を参照)
- 利用者負担の在り方について学ぶ。 (これについては参考文献2 )のpp.223〜228を参照)
レポート課題
課題1 |
福祉サービスの財源調達手段を整理し、そのうえで、利用負担の機能、メリット、利用者負担を軽減する根拠についてのべよ。 |
|---|---|
課題2 |
在宅福祉サービスの利用者負担の在り方について、1.2. についてのべよ。
|
アドバイス
課題1 |
|
|---|---|
課題2 |
|
参考文献
(赤字=大学から送付される必読図書)
- 宮川文男『2025年の世界と日本』東洋経済新報社、1998年
- 大野吉輝『社会サービスの経済学』勁草書房、1991年
- 京極高宣『現代福祉学の構図』中央法規出版、1990年