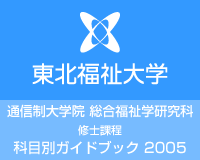
東北福祉大学 通信制大学院 総合福祉学研究科
| 担当教員● | 木村 進 |
|---|
テーマ
家族からみた生涯発達
生涯発達心理学とは、
「人間の受胎から老衰死に至るまでの生涯にわたる心身の発達をあつかう発達心理学。比較的最近までは、発達心理学はもっぱら青年期までの心身の上昇的変化を取り扱い、成人期以後の発達を問題にすることは稀であった。これは、成人期は比較的安定していて顕著な変化はないというステレオタイプ的な信念があったからである。ところが、近年成人期にも下降的変化だけでなく上昇的変化もあることがわかってきた。また高齢化社会の到来によって、高齢者福祉のためにも、高齢者研究の必要性が高まり、それが盛んに行われるようになった。下降的変化についても、高齢者が下降的変化にいかにすればうまく適応して幸福な人生を過ごすことができるのかを研究する必要性が高まってきた。こうして、1960年代から、成人期と高齢期も発達心理学に組み込まれるようになり、全生涯を対象とする生涯発達心理学が誕生した」
(山本多喜司監修『発達心理学用語辞典』)
と説明されている。
発達は積み重ねであるから、子ども時代にどのような経験をしたかが、青年期のあり方に影響し、青年期における経験が成人期に影響を与え、成人期における生き方が老年期に多大に影響するということは当然のことと言えるので、生涯発達心理学という考え方は、きわめて妥当であると思われる。
近年「児童虐待」が大きな社会問題となってきているが、虐待された経験をもつ人が虐待を繰り返す「虐待の世代間伝達」または「世代間連鎖」ということが指摘されている。もちろん虐待された経験をもつ人すべてが虐待を繰り返すわけではなく、そこには発達の問題や環境の問題が関与しているわけであるが、自らの虐待経験をどのように克服するかということは、そういう経験をもつ人にとっては、生涯発達心理学的課題であると言えよう。
本特講においては、生涯発達ということを、家族という視点から理解することを目標としている。家族とのかかわりは、乳幼児期はもとより、児童期、青年期においても大きな意味を持っており、さらには、積極的に家族を作っていくという課題を有する成人期前期、さらには、「空の巣」を前提に家族の再構成を図る成人期後期(初老期)、そして、老年期における家族のあり方 と、人生のそれぞれの節目において大きな意味を持っている。それぞれの発達段階における家族のあり方を追求することによって、生涯発達ということが具体的に見えてくるのではないかということが、本特講の問題意識である。
■研究の視点
- エリクソン、ハヴィガーストの「発達課題」について
- 母子関係の成立をめぐる理論について
- 青年期の「親からの離脱」(精神的自立)について
- 男性と女性のライフサイクルの違いについて
- successful agingとは何か
レポート課題
課題1 |
エリクソンは、最初の発達課題(心理社会的危機)として「基本的信頼感対基本的不信感」を挙げている。これは、母子関係の重要性を指摘したものと解釈されるが、ボウルビーの「アタッチメント理論」を土台にして、母子関係の成立とそのあり方についてまとめなさい。 ただし、内容として、ホスピタリズム(マターナル・ディプリベーション)、インプリンティング(刻印づけ)、スキンシップ理論、子どものテンペラメント(気質)などについて触れること。 |
|---|---|
課題2 |
以下の3問のうち1問を選択して解答しなさい。
|
アドバイス
課題1 |
従来は、母子関係を母親から子どもへの一方的な関係ととらえがちであったがボウルビーのアタッチメント理論が発表されて、初めて「母子相互作用」という視点が一般的になった。レポートの最大の課題は、アタッチメント理論を理解して、この母子相互作用ということをきちんと理解することである。 キーワードとして挙げたインプリンティングとスキンシップ理論は、やはり母子関係の成立について論じたものであるから、アタッチメント理論の補充として理解しておくころが望ましい。 また、ホスピタリズムは、母子関係が早期に喪失した場合の発達への影響について研究したもので、ボウルビーの理論の土台となったものである。さらに、テンペラメントは、母子関係を子どもの側からとらえようとするもので、その点画期的な理論であると考えられる。 レポートは、母子関係のあり方を考えてもらうためのものであるので、ホスピタリズムおよびテンペラメントには触れなくとも合格とするが、頑張って、この点にも言及してほしい。 |
|---|---|
課題2-1 |
児童虐待を発達心理学的に理解するために、その発生要因としての母(父)子関係の病理について論じ、さらに、単に母(父)親だけにすべての責任があるのではなく、環境的要因の影響もあるというところに言及してほしい。 その上で、虐待を受けた子どもの発達への影響について、特にパーソナリティの発達と人間関係の発達に絞って論じてほしい。 |
課題2-2 |
誰でも老年期を迎えるわけであるが、老年期にうまく適応し、幸福な老後の生活を送ることはそう簡単なことではない。1960年代から70年代にかけて論争されたのが「社会的離脱理論」と「社会的活動理論」である。レポートでは、まずこの2つの理論について説明し、それを土台にして、「幸福な老い」にかかわる個人的条件、環境的条件について論じてほしい。 |
課題2-3 |
自我同一性の確立は、青年期の発達課題であるが、「モラトリアム」ということが言われるようになって久しい。自我同一性の確立とは、要するにそれによって大人の仲間入りが可能になるということであるが、レポートでは、まず自我同一性とは何かということについて明らかにし、その発達の経過と条件について論じてほしい。 |
参考文献
(赤字=大学から送付される必読図書)
- 井上勝也他編 1993『新版 老年心理学』朝倉書店
- 下仲順子編 1997『老年心理学』培風館
- 西澤 哲 1994『子どもの虐待〜子どもと家族への治療的アプローチ』誠信書房
- 『講座 生涯発達心理学 1〜5』1995 金子書房
- 繁多 進 1986『愛着の発達』大日本図書