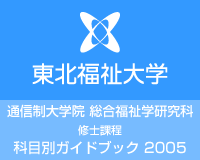
東北福祉大学 通信制大学院 総合福祉学研究科
| 担当教員● | 小松 紘 |
|---|
テーマ
地球家族としての人間と環境:共生のための環境心理学
人間の一生は環境とのさまざまな関わり方によって大きく影響を受けます。その基礎には地理的環境(geographical environment)があり、私たちはそれを土台に作り上げられた人的、社会的、文化的環境の下で基本的生活様式を習得し、またそれらを後世に伝えてきました。しかし生活の個々の場面においては、その場をどう認知したかによって意思決定を行っていることも事実です。これを行動的環境(behavioral environment)といいます。この環境の二重の意味はコフカ(Kurt Koffka:20世紀初めに活躍したゲシュタルト心理学者)によるものですが、彼の行動的環境は現代の認知心理学につながるものでもあります。つまり環境を考えるとき、私たちはその客観的・物理的側面にのみ注意するのではなく、人がその環境をどう認知するか、主観的・心理的側面をも十分に考慮しなければならないということです。
また環境と人間の心身の機能については、朝鮮動乱時の独房での捕虜体験から現代の宇宙飛行まで、人間にとって適度な刺激とはどのようなものかについての話題を提供し続けてきました。この問題は心身の機能に最適な刺激水準の話にとどまらず、さらに快をもたらす刺激の質や揺らぎの話へと展開をみています。
環境とアメニティの問題は、多くの研究が行われている領域ですが、20世紀中ごろからイギリスで始まったOutward Bound活動は、自然のさまざまな活性効果を教育や健康増進のために取り入れようとするものでした。これらの活動は、現在ではnature therapyといわれ、動植物やさまざまな自然環境の癒し効果を活用するholistic(全体的)な療法として多くの研究者や実践家の関心を集めています。
このように多くの生命を育み、計り知れない恩恵を与えてくれる環境に対して、歴史的に人間のみがその恩を忘れ、破壊行為を行ってきたのですが、今そのツケを支払わなければならない段階に来ています。自然破壊行動の動機は、シュプランガー(Eduard Spranger)のいう6つの価値領域のうち経済的価値領域が勝ちすぎるためと思われますが、このような行動の心理的背景を明らかにし、再発を防ぐとともに、環境の回復のための方策を探る努力に、急ぎ力を結集することが人類のなすべき責務でありましょう。
環境心理学の本来の役割は単に人間サイドの快適性や利便性の追求だけではありません。まさに地球家族の一員として、人間が行える、また行わなくてはならない勤めを実践するところにあります。本特講では以上の観点について、書物から学ぶだけでなく、日々の生活を通して、自ら考え実践することを重視したいと思います。
■研究の視点
- 人間行動と環境〜地理的環境と行動的環境
- 刺激水準と心理機能
- 快適環境を求めて
- 自然のもつ癒し効果
- 地球家族としての人間と環境
レポート課題
課題1 |
次の課題の中からひとつ選んで論述しなさい。
|
|---|---|
課題2 |
次の課題の中からひとつ選んで論述しなさい。
|
アドバイス
課題1-1 |
人間の認識には、環境からの刺激情報が感覚器官を経て大脳中枢へと伝えられるデータ駆動型ボトムアップ処理と、まず先に何らかの思いや解釈、感情があって、その結果ある認識が成立する概念駆動型トップダウン処理の存在が知られています。○を『○』、△を『△』と認識する能力は前者の機制によるものであり、シャクトリムシを木の枝と思い土瓶をかけようとして壊してしまうのは後者の機制によるものです。地理的環境は人間の認識以前にある物理的環境であり、行動的環境は地理的環境がどうであれ、人によって認知された環境です。ここに両者の類似点があります。 |
|---|---|
課題1-2 |
狭い宇宙船内の環境は仕事の煩雑さの点では刺激過剰負荷(sensory overload)条件ともいえるし、また隔離された環境であり、さまざまな社会的刺激に乏しいことを考えれば、社会的孤独(social isolation)、または刺激削減(sensory reduction)状況ともみなすことができます。このような条件下においては、人間の心身の機能は一般に正常に機能しにくいので、クルーたちはそれを克服するためさまざまの試みを行っています。 |
課題1-3 |
建築物や庭など、民族固有の文化を反映したものを端的に表現することには本来無理がありますが、日本と欧米の伝統的庭園や建造物を比べてみて、かなり特徴的と思われることは、自然との関わり方、自然の生かし方、取り入れ方の違いです。そこには木と石の素材の違いもあり、狩猟民族と農耕民族といった遠い祖先から受け継いだ血の違いがあるのかもしれません。 |
課題2-1 |
人間の感覚は同じような刺激が持続すると順応現象を起こし、その刺激の印象が薄らぐか消失してしまいます。したがって刺激は変化することによって刺激となり続けることができますが、そこにもある特別の性質をもった『ゆらぎ』の存在が知られています。 |
課題2-2 |
社会主義社会と違って、資本主義社会における街の景観の特徴は看板やネオンサインなど、商業宣伝物の氾濫にあります。自分の街の景観を改めて眺めてみることは、郷土愛をいっそう高めるとともに、他の土地に対する関心と理解を深めるものでもあります。 |
課題2-3 |
共感や思いやりの心は単に身近な人間関係にのみ当てはまるものではなく、地域社会、国、ひいては地球レベルで取り上げられるべき、人間として最も大切な心です。人は自分の価値観に従って行動するとともに、自分の準拠する集団の価値観にも従うので、よい価値観の支配する社会を作ることが大切です。その意味において、今こそ地球家族の一員としての人間について、改めて考えてみることが必要と思われます。 |
参考文献
(赤字=大学から送付される必読図書)
- 岩田 紀 2001『快適環境の社会心理学』(現代応用社会心理学講座2 )ナカニシヤ出版
- 大山正博 1992『改訂版 人間への心理学的アプローチ』学術図書出版
- 北村晴朗・大久保幸郎 1986『刺激のない世界』新曜社
- 鈴木浩明 1999『快適さを測る』日本出版サービス
- 遠山 益 2001『人間環境学』裳華房
- 日本生理人類学会 2000『生理人類学から見た環境の科学』彰国社
- 武者利光 1994『ゆらぎの発想 1/fゆらぎの謎にせまる』NHK出版